グーグル「AIモード」検索、ついに日本でスタート!想定されるSEOへの影響と対処方法とは?
執筆:近添真由(全日本SEO協会認定SEOスペシャリスト)
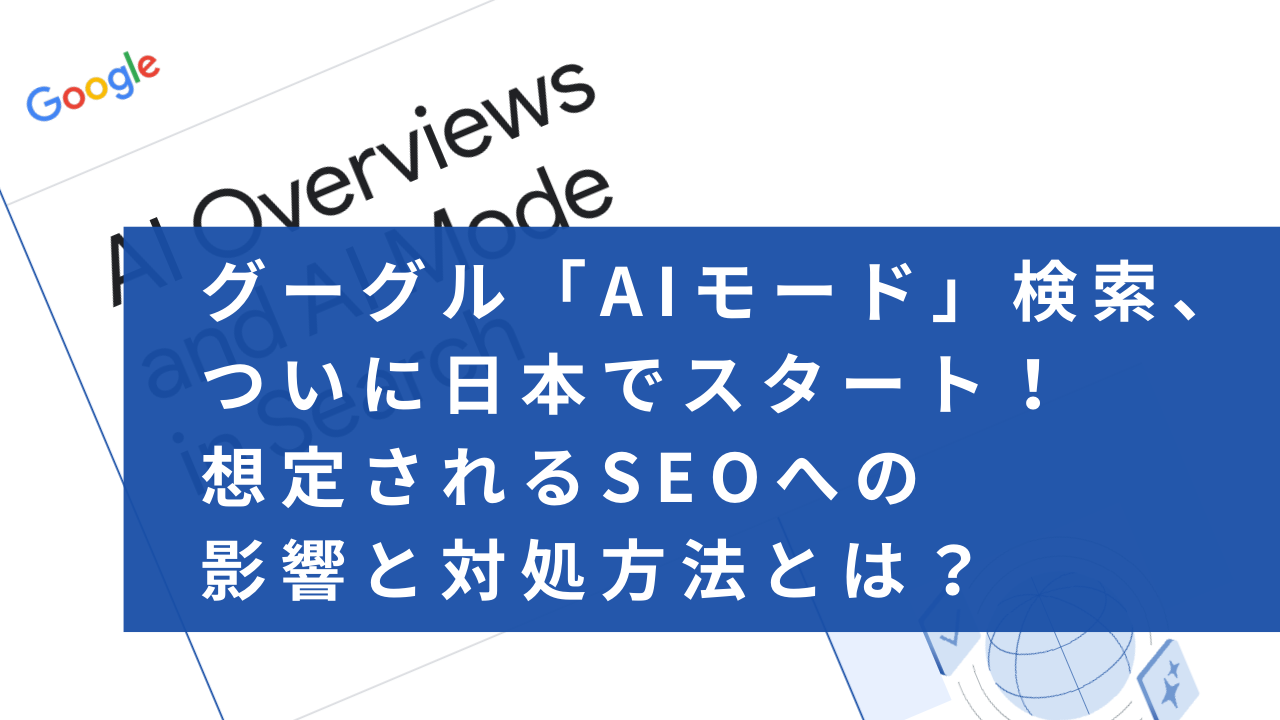
- 1. Google、検索における「AI モード」を日本語で提供開始
- 2. Google AI Mode導入後に起こるユーザー行動の変化
- 2.1. 情報収集手段は、キーワード検索から「会話型」へ移行
- 3. SEO対策における変化
- 3.1.1. 短期的に起こる変化-従来のSEOへの影響
- 3.1.2. 長期的な視点での最重要戦略
- 4. 取るべき対策
- 4.1. AI時代に対応するための新たなコンテンツ戦略の確立
- 4.1.1. 「AIに引用される」ためのSEO戦略
- 4.1.1.1. E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の再評価と強化
- 4.1.1.2. 独自調査や一次情報の創出と活用
- 4.1.2. コンテンツ構造の最適化と視覚要素の活用
- 5. AIモード時代に取り組むべき事
- 5.1.1. 既存コンテンツの棚卸しとリライト戦略
- 5.1.2. トラフィック分析手法の見直し
- 5.1.3. AI時代に求められる新たなスキルと組織体制
- 5.1. 結論と推奨事項
- 6. SEOコンサルタントとしての見解
Google、検索における「AI モード」を日本語で提供開始
2025年9月9日、Google、検索における「AI モード」を日本語で提供開始というニュースがリリースされました。
この記事は、2025年5月に公開されたGoogleのAI Mode in Searchに対する公式な概要レポートをベースに、AIモード導入後のSEO対策の要点と取るべき対策をまとめてご紹介します。
Google AI Mode導入後に起こるユーザー行動の変化
情報収集手段は、キーワード検索から「会話型」へ移行
Google検索は、従来のキーワードマッチングとウェブページへのリンク提供というモデルから、ユーザーの意図を深く理解し、対話的に回答を生成する「AI検索」へと構造的なパラダイムシフトを遂げつつあります。
この転換期を象徴するのが、より複雑なクエリと対話に対応する新機能「AI Mode」です。この変化は、SEO(検索エンジン最適化)の目的を、単に「検索順位を獲得すること」から、AIに引用される「信頼性の高い情報源となること」へと根本的に転換させます。
SEO対策における変化
短期的に起こる変化-従来のSEOへの影響
短期的な視点では、AIによる回答で完結する「ゼロクリック検索」の増加により、単純な情報を提供するウェブサイトのトラフィック減少リスクが顕在化します。
複数の調査では、AI検索がユーザーの疑問に直接回答するため、ウェブサイトへのクリック率(CTR)が平均34.5%も低下していると報告されています 。この現象は、ユーザーがAIの回答だけで情報収集を完結させてしまう「ゼロクリック」行動の増加によるものです 。特に「〇〇とは」「〇〇の意味」といった単純な定義や要約を提供するコンテンツを持つサイトは、その影響を強く受けるリスクがあります 。
一方で、GoogleはAI検索導入後も総クリック数は安定しており、むしろクリックの質が向上したと主張しています 。この主張によれば、ユーザーはAIの回答で表面的な疑問を解決した後、より深い情報や独自の視点を求めてリンクをクリックし、その結果、ウェブサイトに長く滞在する傾向が見られるとのことです 。
今後、AIは一次的な情報収集の役割を担い、本当に深い知識や独自の視点を求めているユーザーのみをウェブサイトへと誘導します。結果として、コンテンツサイトへの流入総数は減少するかもしれませんが、流入するユーザーはより購買意欲やエンゲージメントの高い層である可能性が高まります。
このパラダイムシフトに対応するためには、短期的なトラフィック変動に一喜一憂するのではなく、AIに選ばれる信頼性の高い情報源となるための戦略を構築することが不可欠です。
長期的な視点での最重要戦略
長期的な視点での最重要戦略は、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を強化し、AIが生成できない「人間ならではの付加価値」である一次情報を創出することにあります。具体的には、独自調査、実体験、専門家監修などの要素をコンテンツに組み込むことが、AIに引用される可能性を飛躍的に高めます。
また、AIが情報を抽出しやすいよう、FAQ形式や視覚要素(グラフ、表、画像)を積極的に活用するコンテンツ構造への再設計が求められます。
分析手法も再考する必要があり、従来のPVやCTRに加え、「AIへの引用回数」や「ブランド認知度向上」といった新たな指標で成果を評価する体制の構築が不可欠です。この変革は、単なる技術的対策を超え、企業全体が「独自の価値を生み出す情報発信組織」へと変革する機会を提供します。
取るべき対策
AI時代に対応するための新たなコンテンツ戦略の確立
「AIに引用される」ためのSEO戦略
AI検索時代においてもSEOは重要であり、その本質は「ユーザーに役立つ信頼性の高い情報を提供すること」にあります 。しかし、その目的は「AIに引用される信頼性の最適化」へとシフトします 。
E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の再評価と強化
Googleは、AI Modeの引用枠に表示されるコンテンツは、E-E-A-T指標を満たすものが優先されると説明しています。E-E-A-Tは、AIが情報源として選ぶか否かの最重要シグナルと化しました 。
E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)
- Experience(経験): 実際に商品を使用したレビューや、現場で得られた知見など、実体験に基づく情報が重視されます。
- Expertise(専門性): 特定のテーマに絞ってコンテンツを深く掘り下げたり、専門家による監修を加えたりすることで、専門性の高さを証明します。
- Authoritativeness(権威性): 業界での受賞歴、信頼できるサイトからの被リンク、SNSでの情報発信によるサイテーション増加を通じて、権威性を構築します。
- Trustworthiness(信頼性): Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)の3つの要素から、そのコンテンツが信頼に足るかどうかを評価する指標で、Googleが定める検索品質評価ガイドラインの中で特に重要視されています。
独自調査や一次情報の創出と活用
AIは既存のウェブページから情報を整理・要約するため、ゼロから情報を創造することはできません 。したがって、AIが生成できない「人間ならではの付加価値」である一次情報が、コンテンツの競争優位性を確立する鍵となります。
- ユーザーアンケートとインタビュー: 顧客のリアルな声や疑問点を収集し、コンテンツに反映させます 。アンケート結果をグラフ化することで説得力が増します 。
- 自社独自の事例やデータ: 製品の実測データや顧客インタビュー、成功事例を掲載することで、唯一無二の価値を提供します。
- 専門家への監修依頼: コンテンツの正確性と信頼性を高めます。
一次情報をコンテンツに盛り込む際には、グラフや表を活用して視覚的に分かりやすくし、必ず出典を明記することが必須です。
コンテンツ構造の最適化と視覚要素の活用
AIが情報を抽出しやすいコンテンツ構造に最適化することも重要です。
- 質問と回答(FAQ)形式の有効性: FAQ形式は、ユーザーの疑問に直接答えるため、検索エンジンに「明確な価値」を持つコンテンツとして認識されます。AIが情報を抜粋しやすいよう、1つの見出しに1つの回答を簡潔にまとめる構成が有効です。
- 視覚要素(画像、動画、グラフ)の活用: AI Modeがマルチモーダルに対応するため、コンテンツ制作者は文章だけでなく、画像、動画、音声など多様な形式での情報提供が求められます。オリジナルの図解、インフォグラフィック、YouTube動画、データに基づいたチャートやグラフをコンテンツに組み込むことで、AIが「重要なインサイト」として引用しやすくなります。
- 構造化データ活用意義の再定義: FAQPageやHowToスキーマなどの構造化データは、AIにページ内容を正確に伝えるのに役立つとされています 。しかし、ある検証によると、LLMはトークン化の過程で構造化データの構造を破壊するため、直接的にこれを理解している明確な証拠はないと指摘されています 。この矛盾は、AIが情報を取得するプロセスが複数あることで説明できます。
LLMが直接的なブラウジングで構造化データを活用しないとしても、GoogleのインデックスやKnowledge Graphが構造化データを活用して情報を整理し、LLMの「グラウンディング(情報参照)」ステップで間接的に利用される可能性は高いです 。したがって、構造化データは依然として価値があると言えますが、その価値は「Googleの検索システム全体への正確な情報提供」という側面にシフトしています 。
| 特性 | 従来のSEOとの違い | 具体的なコンテンツ対策 |
|---|---|---|
| 独自性 | 単なる情報の羅列でも通用した | 一次情報(独自調査、実体験)が不可欠 |
| 信頼性 | リンクや権威性が主な指標 | E-E-A-TがAIに引用される最重要シグナルに |
| 構造 | Hタグによる階層が中心 | FAQ形式、視覚要素(表、グラフ)の積極的活用 |
| マルチモーダル | テキストが主軸 | 画像、動画、音声での情報提供が必須に |
AIモード時代に取り組むべき事
既存コンテンツの棚卸しとリライト戦略
AIに代替されやすいコンテンツ(例:単純な情報羅列、定義のみ)を特定し、一次情報や独自の視点を加えてリライトする戦略が必要です 。具体的なフローは以下の通りです。
- 既存記事をAIが読める構造かチェックする: AIが情報を抽出しやすいよう、明確な見出しや箇条書きで構成されているかを確認します 。
- 重複・薄い記事を統合する: 情報が散在しているコンテンツを一つにまとめ、情報深度を高めます 。
- AIが引用しやすいレイアウトへ改修する: FAQ形式、表やグラフ、オリジナルの画像・動画を追加するなど、視覚要素を強化します 。
- 定期的なPDCAサイクルを回す: Google Labsなどを活用し、自社コンテンツがAI Modeでどのように表示されるかを定期的に確認し、改善を繰り返します 。
トラフィック分析手法の見直し
AIモードの普及に対応するため、従来のPVやCTRに加え、新しい指標の導入が不可欠です 。例えば、Google Analytics 4(GA4)のカスタムディメンションや、Ahrefsなどの専用ツールを利用し、「AI経由の流入元」や「引用された回数」を計測する仕組みを構築することが推奨されます 。これにより、総トラフィック量だけではなく、AIからの流入がどの程度ビジネスに貢献しているかを評価することが可能になります。
AI時代に求められる新たなスキルと組織体制
AI時代のSEOは、もはやウェブ担当者やマーケティング部門だけの課題ではありません。E-E-A-Tと一次情報の創出は、企業全体の協力があって初めて達成できる目標です。
- SEOスキルの進化: 従来のキーワード選定に加え、「文脈と検索意図を深く理解するスキル」がより重要になります。AIが生成した情報のファクトチェックや編集能力も不可欠となります 。急速な技術変化に対応するための適応力と継続的な学習が鍵となります 。
- 組織横断的な連携の重要性: 一次情報を効率的に収集するため、営業やカスタマーサポートといった顧客と直接関わる部門との連携が不可欠です。顧客から寄せられるリアルな質問や課題は、新たなコンテンツ企画の貴重な源泉となります。また、法務部門との連携を強化し、著作権やプライバシーといった法的リスクに備える必要があります。
AIに引用されるコンテンツの根幹は、E-E-A-Tと一次情報にあります。これらは、テクニカルなSEO対策だけでは達成できません 。一次情報の創出には社内各部門の協力が必要であり、専門家による監修には社外の協力者を巻き込む企画力も求められます。AI時代のSEOは、企業全体が「独自の価値を生み出す情報発信組織」へと変革することが、真の競争優位性を確立する唯一の方法であることを示唆しています。
結論と推奨事項
Google AI Modeは、検索体験をキーワードベースの断片的な情報収集から、対話型で包括的な情報探索へと根本的に変革するものです。この変化は、ウェブサイトに「真の価値」を問い直し、情報の創造と発信のあり方を再定義する機会を提供します。
AI Modeの将来的な展望は、ウェブサイトの総トラフィックを減少させる一方で、流入するユーザーの質を向上させる可能性を秘めています。このパラダイムシフトに対応するためには、短期的なトラフィック変動に一喜一憂するのではなく、AIに選ばれる信頼性の高い情報源となるための戦略を構築することが不可欠です。
以下に、短期的・長期的な推奨アクションプランをまとめます。
| 期間 | 主要な目標 | 具体的なアクション | 責任部署 |
| 短期 | 既存コンテンツのAI最適化 | - AIに代替されやすいコンテンツの棚卸し - 既存コンテンツへの一次情報(例:アンケート結果)の追加 - FAQ形式や視覚要素(表、グラフ)を用いたリライト - GA4でAI経由の流入計測をテスト的に開始 | マーケティング部、ウェブ運営部 |
| 長期 | AI時代に適合したコンテンツ戦略の確立 | - 一次情報創出を前提としたコンテンツ企画の定常化 - 営業・サポート・企画部門と連携し、一次情報の収集体制を構築 - E-E-A-Tを組織的に強化する方針の策定 - AI利用における法的・倫理的リスクに関する社内ガイドラインの策定 | 経営企画部、コンテンツ戦略部、法務部 |
これらの戦略を組織的に実行することで、ウェブサイトはAI時代においてもユーザーにとって不可欠な情報源としての地位を確立し、持続的な成長を達成できるでしょう。
SEOコンサルタントとしての見解
従来のキーワード型検索スタイルから、会話型に移行することで、これまでのSEO対策で生じていた「狙ったキーワードで上位化したのに、集客につながらない」という状況を回避し、ユーザーにより正しい情報を直接届けることが可能になるのではないかという期待感があります。
SEO担当者は、日々の営業活動の中で実際に質問される「自社のお客様の疑問や意見」に耳を傾け、それに対する正しい回答とその根拠を発信していくという、本来のあるべき営業活動をウェブ上で展開すれば、おのずと「獲得したいユーザー」にリーチできる可能性が高まっていくのではないかと思います。
E-E-A-Tの重要性が高まるという点については、消費者としては正しい可能性が高い情報にリーチできる確率が高まるという点において非常にありがたい事ですが、情報発信をする立場としては苦境に立たされると言わざるを得ないのかなと感じます。
これは、企業の採用活動にも影響してくるのではないかと想像します。採用の際に、自社の専門性を示すうえで有利となる有資格者を雇用したいというニーズが企業側から出てくるのではないでしょうか。また、記事監修を専門に請け負う「監修ビジネスバブル」や、フリーランスの有資格者があちこちから監修を依頼される「監修バブル」が発生するのでは?という気もします。(昔の被リンクバブルのような状態を想像します)
研究者は、【研究のアイデアを考える→実験する→分析する→論文を書く→雑誌に投稿する】というサイクルを繰り返しています。こうして発表した論文は、他の研究者の論文に引用された回数やほかの研究成果に及ぼした影響などによって評価を得て行きますが、SEOやAIOは完全にこの仕組みと同じだな、と感じます。
これからのウェブ集客は、自分が提供する情報が、オリジナルな一次情報として世の中にどう作用するのか、という点に焦点を当てて企画を組み立て発信をしていく「企画力」や「発信力」の向上が求められているのだと感じています。
企画力に強みを持つコクーンとしては、「いかに、影響力を持つ一次情報の発信者になれるか」という視点をコンサルティングにも取り入れて行きたいなと思います。


